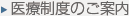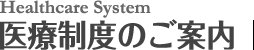B. 作製する前に予め申請が必要なもの(更生用装具等の作製の場合)
なお、対象者が補装具を作製する場合には、予め所定の申請を行う必要があります。
(一部、厚生労働省より抜粋事項を記載しております)http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html
1.申請
申請は、お住まいの市区町村役場で申請を行う事ができます。申請の際は身体障害者手帳及び印鑑をご持参のうえ、お住まいの市区町村役場でお手続き
を行って下さい。
なお、申請は、予め義肢・装具製作業者などに現在お使いの補装具の適合状態及び耐用年数などをチェックを受けてから行うことを
お勧めいたします。
(1) 公費負担
補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を
補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)
(2) 利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
〈所得区分及び負担上限月額〉
| 生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。
※ 生活保護への移行防止措置あり
*厚生労働省より抜粋事項
2.医学的判定
医学的判定とは、医師(自立支援法に基づく主として育成医療等を担当する医師「指定医」をいう)による医学的な見地から、その補装具が対象者にと
って、必要であり、また有用であるかの判定を行うことをいいます。
この医学的判定には、「書類判定A」または「直接判定B」の2つがあります。
いずれの方法にしても、原則として、身体障害者更生相談所の指定医が作成した補装具費支給意見書の提出が必要となります。
なお、この医学的判定で作製の許可(支給決定通知)が得られなければ、業者は補装具の製作に取り掛かることが出ません。
医学判定は、下記のA・Bいずれかの方法となります。
A 書類判定
書類判定となる場合は、今回、作製を希望する補装具と前回作製した補装具都の内容に大きな変更がない場合、または、直接判定を行うことが困難な
場合が対象となります。具体的には、義足などの膝継手や足部を同一のものに交換する場合は高次医療装置等を使用している場合などです。
尚、書類判定であっても、義肢・装具製作所の見積りは必要となりますので予め担当業者にお問い合わせ下さい。
B 直接判定
直接判定は、書類判定とは異なり、※判定所などで行う医学的判定をいいます。
医学的な判定が必要となる場合は、自立支援法の適用を受けて初めて補装具を作製する場合や、前回の見積り内容に大幅な変更がある場合(具体的
には、義足のソケット交換や義足パーツをより上位のものに変更する場合等)です。
直接判定の場合は、基本的には患者さま(又は、患者さまとご家族など)及び義肢・装具製作業者で判定所を訪れ、医学的判定を受けます。
※判定所は身体障害者更生相談所となります。
3.支給決定通知
医学的判定を受けてから、約1~2カ月ほどすると、支給券又は支給決定通知書(以下「支給券」という)というものが患者様のご自宅に郵送で届きま
す。支給券には、補装具の名称、患者様の自己負担金などが記載されています。(次回作製する際に、耐用年数などの確認に使用できるためコピーをお
手元に保存して下さい)。
支給券が届きましたら装具の作製に取り掛かることができますので、業者に連絡し、日取りの調整を行って下さい。
4.仮合せ・引渡
仮合せ・完成は業者と日取りの調整を行って下さい。また、自治体によっては、完成判定を行わない代わりに引取時に受領の署名をする場合があります
ので担当業者にご確認ください。
また、支給券に自己負担金の記載がある場合は引取時に業者にお支払い下さい。
※自治体又は作製する補装具によっては、仮合せ時に適合判定を行う場合もありますので、医学的判定時にご確認ください。
5.適合判定
適合判定では、補装具が見積どおり作製されいるか、生体に適合しているか、又は、患者様の就労、就学もしくは日常生活に機能的に適合しているかな
どをチェックされます。
この判定で、承認されれば無事、補装具の完成となります(次回作製する際は、今回作製した補装具の領収書の日付に基づいて耐用年数を加味して作製
することとなります)。
なお、適合判定も、医学的判定と同様に、書類判定と直接判定のいずれかにより行われます。
補装具の購入費用または修理費用を支給しています。 なお、この制度をご利用いただくにあたり以下の2点にご注意ください。
【注意点】
1.補装具の購入費または、修理費の支給を受けることができる方は、障害補償給付の対象となる方となります。
対象となる方は労災保険法による障害補償給付の適用を受ける方、または、受ける見込みである方となります。
詳しくは下記のリンクから検索することができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pamphlet_faq.html
2.補装具の購入費の支給または修理費の支給は、あらかじめ申請が必要となります。
作製依頼前に所轄労働局に手続きを行う必要があります。(下記、手続きの流れをご参照ください)。
障害補償給付の申請の流れは下記の表のとおりです。なお、患者様に行って頂くお手続きは、下記の表中の☆(1.申請、4.注文、5.仮合せ・引渡)となります。
1.申請 ![]()
患者様より義肢・装具作製のため所轄の労働局へ『義肢等補装具購入・修理費用支給申請書』を提出して頂きます。
2.審査
労働局において内容の審査
3.承認
労働局より患者様の元へ『支給承認書』 を郵送等にて交付
4.注文 ![]()
『支給承認書』が申請者様お手元に届きましたら、義肢・装具製作会社の方へ、義肢・装具の作製のご注文を行って下さい。(義肢・装具の作製を開始)
※支給承認書をご持参下さい。
5.仮合せ・引渡 ![]()
義肢・装具の仮合せ等を経て義肢・装具が完成(仮合せ、完成等は日取り等は義肢装具製作会社にご相談下さい。)
※受領の署名を頂きますので印鑑をご持参下さい。
(印鑑は、三文判で構いません)
患者様に行って頂くお手続きは、下記詳細をご参照ください。
患者様に行って頂く手続きは上記の1.申請、4.注文 、5.仮合せ・引渡の3つになります。
以下、それぞれの詳細についてご説明いたします。
1.申請 ![]()
義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする患者様は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」(以下「申請書」)を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。
また、義肢、筋電電動義手、上肢装具、下肢装具及び車いすなどについては、義肢等の製作・修理に当たり、採型指導医による採型指導を受けることが必要となります。
これらの申請に当たっては、患者様は申請書の所定欄に希望する採型指導医療機関名(労災指定病院で義肢装具製作会社が在中しているところをお勧めいたします)をご記入下さい。
なお、申請の際は、「労働保険番号」及び「年金証書番号」などを記載する欄がありますので、受給者証などと印鑑をご持参のうえ、お手続きをお済ませください。
2.注文 ![]()
所轄労働局より、「支給承認書」が届いたら、その届いた支給申請書の一式(※)をご持参のうえ、申請書に記載した医療機関で採型指導お受け下さい。
その際、上記医療機関に義肢・装具製作会社が在中していない場合は、お近くの義肢装具製作会社等へご相談下さい。
(※)支給承認書一式
| 書類名 | 内容 |
| 義肢等補装具購入・修理費用支給承認書 | 主な内容(作製するもの、個数など) |
| 採型指導依頼書 | 医療機関に記載して頂く書類 |
| 証明書 | 引渡時又は引渡後に適合のチェックの際に医師に記載して頂く書類 |
| 義肢等補装具(購入・修理)費用請求書 | 義肢・装具製作会社が作製した義肢・装具の金額を記載する書類 |
| 義肢等補装具(購入・修理)費用内訳書(殻、骨格構造義肢用、装具用) | 義肢・装具製作会社が作製した義肢・装具の金額の内訳を記載する書類 |
| 適合判定結果について | 筋電義手を作製した場合の適合のチェックの際に医師に記載して頂く書類 |
| その他 |
3.仮合せ・引渡 ![]()
仮合せ・引渡の日取りは義肢装具製作会社ご相談ください。
なお、医師の適合のチェックを受けて頂く必要があります(医師に証明書に)ので、引取日または引取日後で上記の医療機関で医師の診察をお受け下さい。